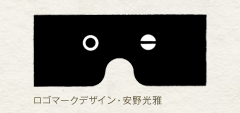
当財団のロゴマークは、画家・装幀家・絵本作家の安野光雅氏に描いていただきました。
安野氏は生前の河合隼雄と交流が深く、多くの著書の装幀を手がけられています。
ロゴマークと河合隼雄について、週刊朝日2013年1月25日号の安野氏のエッセイ「逢えてよかった」で紹介されました。

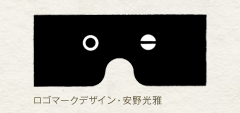
当財団のロゴマークは、画家・装幀家・絵本作家の安野光雅氏に描いていただきました。
安野氏は生前の河合隼雄と交流が深く、多くの著書の装幀を手がけられています。
ロゴマークと河合隼雄について、週刊朝日2013年1月25日号の安野氏のエッセイ「逢えてよかった」で紹介されました。
このたび、河合隼雄と、
詩人・児童文学作家の長田弘さん(1939-2015年)との対談
『子どもの本の森へ』が、岩波現代文庫から出版されました!
本書『子どもの本の森へ』は、
子どもの本についての長田弘さんと河合隼雄の対談が
1994年2月から1995年6月にかけて雑誌連載され、
さらに1997年に本書のために対談したものを加えて、
岩波書店から1998年2月に刊行されました。
それが、四半世紀以上を経て、
河合俊雄代表理事による「解説」を付す形で、
新たに文庫化されました。
新年あけましておめでとうございます。
全国的にさわやかな晴天に恵まれたようです。
2025年の今年の干支は、巳年。
へびは脱皮を繰り返すことから、「生命力」や「再生」を象徴するとか、
「巳」の原字が、子宮が胎児を包む様の「包」の中と同じであることから、
植物の種子ができ始める時を示す、などとされているようです。
東アジア圏でも、へび(巳)がウロボロスを象徴するとは不思議ですね。

京都・玄武神社
第1回 藤原辰史 『ナチスのキッチン 「食べること」の環境史』 (2012年5月 水声社)
第2回 与那原恵 『首里城への坂道:鎌倉芳太郎と近代沖縄の群像』 (2013年7月 筑摩書房)
第3回 大澤真幸 『自由という牢獄 ―責任・公共性・資本主義 ―』(2015年2月 岩波書店)
第4回 武井弘一 『江戸日本の転換点-水田の激増は何をもたらしたか』(2015年4月 NHKブックス)
第5回 釈徹宗 『落語に花咲く仏教-宗教と芸能は共振する-』(2017年2月 朝日新聞出版)
第6回 鶴岡真弓 『ケルト再生の思想―ハロウィンからの生命循環』(2017年10月 筑摩書房)
第7回 藤井一至 『土 地球最後のナゾ─100億人を養う土壌を求めて』(2018年8月 光文社新書)
第8回 小川さやか 『チョンキンマンションのボスは知っているーアングラ経済の人類学』
(2019年7月 春秋社)
第9回 石山徳子 『「犠牲区域」のアメリカ 核開発と先住民族』(2020年9月 岩波書店)
第10回 森田真生 『計算する生命』(2021年4月 新潮社)
第11回 國分 功一郎『スピノザ ——読む人の肖像』(2022年10月 岩波書店(岩波新書))
第12回 湯澤 規子『焼き芋とドーナツ 日米シスターフッド交流秘史』 (2023年9月 KADOKAWA)
第1回 西加奈子 『ふくわらい』 (2012年8月 朝日新聞出版)
第2回 角田光代 『私のなかの彼女』 (2013年11月 新潮社)
第3回 中島京子 『かたづの!』 (2014年8月 集英社)
第4回 いしいしんじ 『悪声』 (2015年6月 文藝春秋)
第5回 今村夏子 『あひる』 (2016年11月 書肆侃侃房)
第6回 松家仁之 『光の犬』 (2017年10月 新潮社)
第7回 三浦しをん 『ののはな通信』(2018年5月 KADOKAWA)
第8回 該当作品なし
第9回 寺地はるな 『水を縫う』(2020年5月 集英社)
第10回 いとうみく『あしたの幸福』(2021年2月 理論社)
第11回 吉原 真里『親愛なるレニー レナード・バーンスタインと戦後日本の物語』
(2022年10月 アルテスパブリッシング)
第12回 八木 詠美『休館日の彼女たち』(2023年3月 筑摩書房)
第12回 河合隼雄学芸賞
〈選考委員〉内田由紀子 中沢新一 山極壽一 若松英輔 (五十音順)
□授賞作□
『焼き芋とドーナツ 日米シスターフッド交流秘史』
湯澤 規子(ゆざわ・のりこ) (2023年9月28日刊行 KADOKAWA)

※特定非営利活動法人 文化創造 および それに付随する河合隼雄公式サイトはこちらのサイトに統合・移転いたしました。