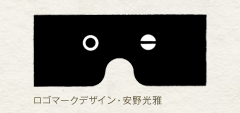
当財団のロゴマークは、画家・装幀家・絵本作家の安野光雅氏に描いていただきました。
安野氏は生前の河合隼雄と交流が深く、多くの著書の装幀を手がけられています。
ロゴマークと河合隼雄について、週刊朝日2013年1月25日号の安野氏のエッセイ「逢えてよかった」で紹介されました。

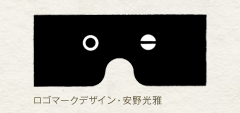
当財団のロゴマークは、画家・装幀家・絵本作家の安野光雅氏に描いていただきました。
安野氏は生前の河合隼雄と交流が深く、多くの著書の装幀を手がけられています。
ロゴマークと河合隼雄について、週刊朝日2013年1月25日号の安野氏のエッセイ「逢えてよかった」で紹介されました。
第8回 河合隼雄学芸賞
〈選考委員〉岩宮恵子 中沢新一 山極寿一 鷲田清一(五十音順)
□授賞作□
『チョンキンマンションのボスは知っているーアングラ経済の人類学』
2019年7月30日刊行 春秋社
小川さやか(おがわ さやか)
河合隼雄の『イメージの心理学』は、
青土社の伝説の雑誌『イマーゴ』の創刊号(1990年1月)から
1年間連載されたものを1冊の本にまとめられたものです。
それからちょうど30年経た2020年4月下旬、新装版としてよそおい新たに、
青土社から復刊することとなりました!
表紙のイラストやデザインは1991年版と変わらずそのままに、
ですがソフトカバーになった分、ちょっとばかり軽量化が実現(笑)。
さらに、今回の新装版には、詩人で河合隼雄の盟友である、
谷川俊太郎さんによる「新装版へのあとがき」も寄せていただいていています。
福井新聞の記事「地方こそ文化の宝庫」の中で、河合隼雄のことが触れられています。
ちょっと前の新聞記事になりますが、
2020年2月23日付の福井新聞の記事(5面)、
「ふくい日曜エッセー・時の風」コーナーの中で、
文化庁総括・研究グループ研究官の朝倉由希さんが、
「地方こそ文化の宝庫」という文章を寄せています。
2040年(!)の福井県を見据えた将来構想を作る
「長期ビジョン推進懇話会」の委員を務める朝倉さん。
長いスパンで地方の将来を見据える上で、
「文化力」は重要なキーワードだと注目されています。
この「文化力」という言葉を公式に使用し、全国に積極的に広めたのは、
文化庁元長官の河合隼雄であったことに触れ、
「人が文化芸術の力で心が豊かになるのと同様、社会も文化芸術の力で元気になる」
という文化庁長官就任当時の河合の言葉を取り上げています。
朝倉さんの記事はこちらで読むことができます。
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1034582
(※会員登録が必要です。登録月は無料です。)
福井県のみならず、
全国各地の、 あらゆる地域の、あらゆる人々の多様な ”文化の力=文化力”は、
今まさに見直され、大切にされるべき時ではないでしょうか?
さらに、河合隼雄の考える「文化の力」について、
『日本文化のゆくえ』(岩波現代文庫,2002/2013)も
合わせて読んでみてはいかがでしょうか?
約20年前に書かれた本ですが、とりあげられているテーマ
――個人、家族、教育、仕事、消費、科学技術、異文化、夢と遊び、芸術、死、宗教、倫理――は、
まさにどれをとっても現在、今日のわれわれが直面している問題です。
この20年で社会は大いに変化してきたとはいえ、
河合隼雄の日本社会と文化を貫く普遍的な視点から、
あらためて現代を振り返ってみることで、 新しい気づきを得る機会になるに違いありません。
すっかり更新が遅くなりましたが、昨年10月に文庫版で復刊された、
『声の力―歌・語り・子ども』
(河合隼雄・阪田寛夫・谷川俊太郎・池田直樹;岩波現代新書)
のご紹介です。
今、世界はCOVID-19の感染拡大の最中にあり、
さまざまに錯綜する声――切実で悲痛な声、 怒りの声、はげましの声、感謝の声などなど――
が巷に飛び交っています。
また、「3つの密を避ける」ことの必要性から、
私たちは他者との間に物理的な距離をとらなくてはならず、
その疎外感に、寂しさや不安、心細さも実感しているかもしれません。
そんななか、“声”の、人と人とを結びつける“力”について、あらためて考えさせられる一冊です。
第7回 河合隼雄学芸賞
〈選考委員〉岩宮恵子 中沢新一 山極寿一 鷲田清一(五十音順)
□授賞作□
『土 地球最後のナゾ─100億人を養う土壌を求めて』
2018年8月 光文社刊
藤井 一至 (ふじい かずみち)
□著者略歴□
土の研究者。国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所主任研究員。1981年富山県生まれ。京都大学農学研究科博士課程修了。博士(農学)。京都大学研究員、日本学術振興会特別研究員を経て、現職。カナダ極北の永久凍土からインドネシアの熱帯雨林までスコップ片手に世界各地、日本の津々浦々を飛び回り、土の成り立ちと持続的な利用方法を研究している。第1回日本生態学会奨励賞(鈴木賞)、第33回日本土壌肥料学会奨励賞、第15回日本農学進歩賞受賞。著書に『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(山と溪谷社)など。
□授賞理由□
地球を構成する12種類の土を求めて、あらゆる地域でそれを体で確かめ、これをもとに現代の環境問題や食糧問題、人口問題を含めた地球課題を闊達な筆致で論じ、新しい視点を提供する一冊。
□受賞のことば□
このたびは、身に余る賞を頂きありがとうございます。河合先生の研究しておられた文化(カルチャー)の語源は地を耕すことにある、と聞いており、そこにご縁を感じております。
※正式な受賞の言葉や選評は「新潮」8月号(7月5日発売)誌上で発表されました。
※特定非営利活動法人 文化創造 および それに付随する河合隼雄公式サイトはこちらのサイトに統合・移転いたしました。