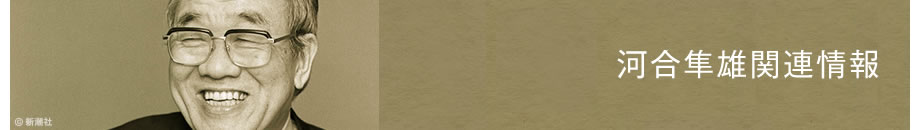2025年11月9日(日)、第13回河合隼雄物語賞・学芸賞記念講演会が
京都大学の会場とオンラインとで開催されました。
河合家といえば「雨」。
当日も雨脚が強く、現地ご来場いただきました皆様には感謝申し上げます。
-342x480.png)
司会は京都大学 人と社会の未来研究院教授であり、
河合隼雄学芸賞選考委員の内田由紀子さんです。
冒頭では、河合俊雄代表理事より挨拶がありました。
2年前に河合隼雄の次男・幹雄さんが亡くなられ、
幹雄さんの専門の法社会学のことや父について、
語られなかったことが多かったと感じていること、
そして「伝えられるうちに伝えていく必要がある」と考え、
企画に至った経緯が語られました。
今回は、河合隼雄の三男であり、
当財団評議員の河合成雄さんの講演『河合隼雄の度重なる西洋との出会い』を企画。
特に長男である自身は早くに家を出たので、その後の父・隼雄と、
自分とは6歳年下の三男・成雄さんとの関係や語らいについて、われわれ同様、
俊雄代表理事も楽しみにしていると話されました。
成雄さんはこれまであまり父について語ってこなかったのだそうです。
しかし、河合隼雄が自身についてはじめてまとまって語った著書
『未来への記憶』(岩波新書、現在は『河合隼雄自伝』新潮文庫)
は父が62歳の時であったこと、
そして今自身が同じ年齢となり、このように父について語る機会を得たという、
不思議な縁に触れられました。
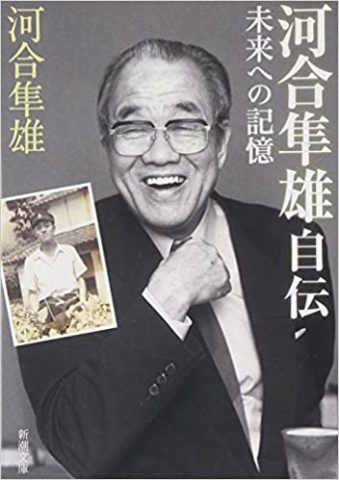
〇家族と西洋文化との関わりと「3」という数
河合隼雄が育った家族との関係や丹波篠山での様子は
『泣き虫ハァちゃん』(新潮文庫)でよく知られています。
西洋の音楽や小説を長兄、次兄から教えてもらい、
隼雄の父・秀雄は、戦前・戦中もクリスマスを祝うなど、
当時としては珍しく西洋文化の影響を受けた家庭環境でした。
また、河合隼雄自身が育てた家庭では、
夫婦がまずあって世界ができていくように、
核家族を大切にする考えを持っているように思われました。
そして3人の息子について「3は大事や、2と比べて関係性が3倍になる」
と語っていたことや、「親子といっても、兄弟といっても、神話の世界では殺し合いの関係だ」
などと言っていたことを振り返り、だからこそ家族を大事にしたのではないだろうか、
と成雄さんは述べました。
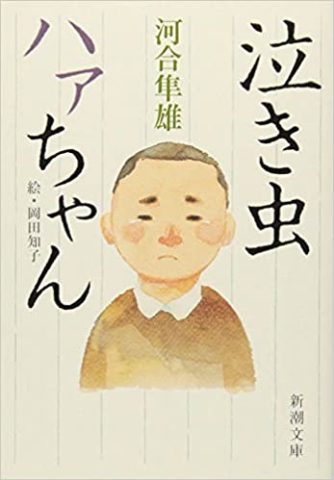
〇父と息子たちの関わり・児童文学
奈良の家には多くの本があり、『子どもの宇宙』(岩波新書)でも
ヨーロッパの作品が多く取り上げられているように、
児童文学については特にヨーロッパの作品を多く読みました。
河合隼雄は座右の銘などは持たないと言っていたものの、
『モンテ・クリスト伯』の「待て、しかして希望せよ」
という言葉を大切にしていたエピソードに触れ、
心理療法家としての父にとっての座右の銘に近い言葉ではなかったかと振り返りました。
成雄さんがイタリア思想・文学を専門にしたのも、
父から「日本のことを考えるにしても、まず西洋のことをやるのがいい」
と勧められたことがある意味きっかけであったそうです。
父自身も、ヨーロッパの学問を小さい頃から身に着ける有利さを感じていたからではないでしょうか。

〇イタリアでの父との出会い
成雄さんがイタリア留学中、父・隼雄がアスコナのエラノス会議や
国際箱庭療法学会に出席するついでに3度イタリアに訪れ、
二人で教会や美術館を巡った思い出が、
お互いに写したスナップ写真とともに紹介されました。
成雄さんは父と一緒に数々の建築や美術作品を観ましたが、
たとえば『聖母子像』では「なぜ、イエスとマリアは視線を合わせないのだろう?」、
イエスの『磔刑図』では「日本人には贖いということはわかるのだろうか?」など、
それらをめぐっての父と息子の対話など、
さりげなくも深く印象的なやりとりがいくつも紹介されました。
マルシリオ・フィチーノ(Marsilio Ficino,1433-1499)は成雄さんの専門で、
15世紀のイタリア最大の思想家について、父・隼雄は、
スピリットSpiritをどう定義するのか、
その歴史を知りたがっていたそうです。
フィチーノが活躍した時代は、
イメージの世界、無意識の世界が自明のものとしてあった時代であり、
スピリットは、魂(アニマ Anima)と身体・物体(Corpus)を結び付けるもの
と考えられていることを紹介しつつ、
成雄さんは、おそらく父・隼雄はそこから、ユング心理学におけるアニマや、
スピリットについて考えを巡らせていたのかもしれないと、父の思索をたどります。
〇河合隼雄の晩年の構想
河合隼雄は最後、学問的な本を2冊考えていた。
「受胎告知について書きたいんや」と語っていたこと、
また能のシテとワキについて考えていることを聞いていたそうです。
しかし、それらについて河合隼雄が何をどう書こうとしてかはわからないままに
亡くなってしまいました。
能におけるシテは、死者の世界、向こうの世界のことを語ります。
心理療法家としての父・隼雄は、ずっとワキの仕事を職業としてやっていたのかもしれません。
そしてどこかで死ぬことをずっと意識していて、
シテとしてどうやって向こうの世界に行くのか考えていたのではないか。
われわれがワキとして、父をシテとして向こうの世界へ送り込むことを
今でもやっているのではないかと述べ、
最後に、成雄さんは、ベネチアのラグーンの彼岸から
手を振っている河合隼雄の写真を我々に紹介し、
講演を締められました。
〇ディスカッション
後半はディスカッション形式で、司会の内田さんがさまざまな質問を投げかけ、
成雄さんと俊雄代表理事がざっくばらんに答える形で進行しました。

児童文学については、父と3兄弟で
「これは読んだ方がいい」「これは好きだ」と話すことはあっても、
内容についてはあまり語らなかったそうです。
父はストラクチャー(構造)を見る力が高く、
物語の構造に強い関心を持っていました。
たとえば俊雄代表理事が『ホビットの冒険』を勧めて読んでくれたときは、
一言「これは女性が出てこないね」など、
そういう見方をしていたことがわかります。

父は、誰かに、どこかで一度話してしまうともうそれで満足してしまって
本に書かなかったことも多かったそうです。
講演をするときは、レシートの裏に話すことを3,4つメモして、
それだけで70分とか90分とか話していました。
本を書く時は、書く瞬間に深めて書いていくスタイルでしたが、
本や講演には、ストラクチャーがしっかりあり、
ポイントがクリアでストーリー性がある。
それは日本語でも英語でも変わらないのではないか。
しかし何を考えているかとか、
感想とかはほとんど家族の中では話さなかったことを振り返ります。

俊雄代表理事は、成雄さんの今日の話を聞いていて、
初めて聞いた話もとても多かったと述べ、
それはイタリアで父と成雄が時間を共有したのが大きかったのではないか、
日本では、父は束縛も多くスケジュールがびっしりだったため、
旅行の時にようやくじっくり過ごすことができたのではないかと思い巡らせます。
また、成雄さんの講演の中で取り上げられたフィチーノの思想について、
ユング派分析家のJ.ヒルマンが評価していたことは知っていたが、
しかしヒルマンが注目したのはアニマのことが中心で、
スピリットのことはどうだったのだろうかと興味を持ったと語ります。
さらに、受胎告知のこと、
能のワキとシテのことを書こうと考えていた話は今初めて聞いてびっくりした。
何をどう考えていたのだろう?わからないとしながらも、
さまざまに兄弟二人で思い巡らせる時間となりました。

今回の講演会を通じて、
河合隼雄の家族の前でのリラックスした姿が、
あるいは父としての姿が、
写真とエピソードを通して垣間見ることができました。
それと同時に、
河合隼雄が最後まで「語らなかったこと」「書かなかったこと」があり、
今を生きるわたしたちの宿題として残されていることも
浮かび上がってきたように感じられました。
今回もたくさんの皆様にご来場・ご視聴いただきまして、ありがとうございました。